『テレパシー』サイドストーリー
掲載日 2024/12/05
読了目安 15分
【あらすじ】
源元 政《みなもと まつり》とその恋人 加矢《かや》の物語。政は『テレパシー』にて、メインキャラクターだった高木の友人として登場している。
良好な関係の政と加矢は、あることをきっかけに大きくヒビが入ってしまう。しかし、加矢には意見をゆずれない理由になった過去があり……。
『ホモフォビア』単体でも読むことが出来ますが、若干『テレパシー』のネタバレが含まれます。
『ホモフォビア』テレパシーサイドストーリー
【プロローグ】
ありふれた幸福な家庭
母は専業主婦で家に帰れば美味しそうな匂いがしていたし、父は仕事が忙しくても出来るだけ家族との時間を大切にする人だった。
けれども、それは突然に
学校から家に帰ると母のおかえりという声はなく、そのかわり泣き叫ぶ声が聞こえた。リビングへかけつけると泣き崩れている母と、それを冷たく見おろし押し黙る父が立っていた。
「何があったの!」
尋ねても、父も、母も、なにも答えはせず。
そのまま、あの冷酷な男は私達を置いて出ていった──。
【私の恋人】
[おん、おん。ほぅか、良かったなぁ。蘭ちゃんのこと、ちゃんと受け止めてくれたんやな]
私の恋人は先程から電話に夢中で、いっこうに話し終わる気配がない。最近はレポートに手一杯でなかなか会えなかったところを家に呼んでくれたものだから、ゆっくり出来ると思っていたのに。けれども彼の雰囲気と口調から大事な話をしていることは分かるから大人しく待つほかない。
[えぇよ。またいつでも言いや。おん。またな]
プツ、と電話が切れたのを確認し携帯から顔をあげる彼にささやく。
「浮気?」
もちろん、そんなことがあり得ないのは分かっている。けれども蘭ちゃんのことをあまりに大事にしているので少しばかり意地悪がしたくなったのだ。
すぐに彼はあわてて首をふる。
「友達、友達!」
「それにしては随分と大事そうに名前呼んでたじゃない蘭ちゃん♡ですって」
わざとらしく可愛い声を出してみせると、もっと彼はあわてた。
「ちゃう、ちゃうて! 俺は加矢一筋やから! 蘭ちゃんは昔からの付き合いっちゅうか」
「分かってるわ。そんなに必死に言わなくても……冗談よ」
彼はホッとして背中を丸めて息をつく。
「どんな子なの? その蘭ちゃんて」
彼がとても大事に思っているらしい子のことが気になった。純粋な好奇心、いや、その中に隠れた嫉妬もあった。
「蘭ちゃんは一緒に弓道をやっとってなぁ。めちゃめちゃうまいねん。うちのじいちゃんも褒めるくらいでな」
「あのお祖父様が?」
彼の祖父は弓道の師範でとても有名な人。普段は明るくて優しい人だけれど、ひとたび袴を着て道場に入れば鬼神のように恐ろしく、威厳のある人だった。何度か弓を引くところを見たけれど、まったく弓に詳しくない私でもその精神性を垣間見ることが出来た。
あの、弓に関しては僅かの妥協も許さない人が褒めるというのだから、その子は本当にすごいのだろう。
「ほいでも、抜けとるとこのあるやつでなぁ。この間なんか上衣着るの忘れて袴はいてしもて結局倍の時間かかっとったわ」
「やだ、うっかりしてるのね。でもちょっと気持ちは分かるわ。私も道着を着る時ぼんやりしてて順番を間違えることがあるもの」
同じ道着でも私は剣道の道着だったが、着付けはそう変わらないはずだ。
そして笑ったあとにふと気づく。着替え? 袴??
「……いくら仲が良くても、女の子の着替えを見るのはどうかと思うわ……」
「えっ? え?」
彼も天然なところがある。いくらその蘭ちゃんが許してくれても、流石に問題があるだろう。
「ちゃう! ちゃうんよ! 蘭ちゃんは男の子やで! 俺かて女の子と一緒に着替えたりせぇへんわ!」
「えっ。男の子なの? ちゃんだからてっきり」
「確かに女の子みたいに綺麗な子なんやけど、男の子やから大丈夫やで」
「それなら良かったわ」
なんだ。それなら、なにも気にすることは無かった。いくら親しくても男なら
なにも奪われることはないのだから。
【すいか】
噂の蘭ちゃんはどうやら恋愛について悩んでいるらしかった。あれからも度々電話やメールでやり取りをしているのを見かけた。
彼は誰かといるときは目の前の人を大切にする人だったけれど、蘭ちゃんに関しては私に一言あやまってからメールを確認したり、場合によってはすぐに返事を打ち込んだ。それほど大切なのだろう。
私は彼のそういう強い愛情を持っているところが好きだ。
いつも堂々としていて、中途半端に誤魔化したり隠し事は絶対にしない。
けれどもそんな彼がたった一度だけ、言葉を濁したことがあった。
いつだったか蘭ちゃんの存在を私が知って、写真を見せてもらったときのことだった。
明るく笑う彼の隣で、無表情な線の細い男の子がいた。けれどもその容姿は長い前髪に隠れてよく分からなかったのだ。
「もうちょっと顔が見える写真はないの?」
尋ねると彼は写真フォルダを探すこともなく言った。
「蘭ちゃんは顔見られんの嫌いやからなぁ」
「恥ずかしがりなの?」
「んー……まぁ、そんな感じやな」
彼がそんな曖昧な返答をするのは珍しかった。さらに追求しようかとも思ったけれど、聞いてほしくは無さそうだった。それに、彼がはっきり言わないということは、聞いたとて教えてくれることはないだろうと思った。
けれども謎に包まれた『蘭ちゃん』に相まみえる機会がやってきた。というのも、別に彼が用意したわけではなくそれはただの偶然。
蝉の声がうるさい夏の日に、私は近所のおばさんにもらった大きなスイカを一人では食べ切れないし、せっかく上等なものだから彼とそのお祖父さんと一緒に食べようと思い立った。
夏休み中は暫くの間、お祖父さんの大きな家に寝泊まりしているのを知っていたから一言メッセージを送ってお祖父さんの家を尋ねた。メッセージに既読はついていなかったが、彼も夏休み中はいつ遊びにきても構わないと言っていたし、それに去年の夏も何度か返事が帰ってこないまま彼の家についてしまったが迷惑そうな顔はしていなかった。むしろお祖父様ともども嬉しそうに迎えてくれたので私もそれに慣れていった。
ピンポーン 立派な門についたインターホンを押す。ほどなくして袴姿の彼が出てきた。
「練習してたの? ごめんなさい邪魔して」
「平気やよ。ちょうど終わって着替えようと思ってたところやから。ちょっと今、友達が遊びにきとるから……あ、スイカ持つで!」
編まれた袋に入ったスイカを持ち美味そうやなぁ! と嬉しそうに言いながら家の中にいれてくれる。
居間にいくとお祖父様が冷たい緑茶をいれてくれて、彼にさっさと着替えて汗を流してこい、とたしなめる。
「加矢さん、すまんね政が、シャワーも浴びずに」
「気にしませんよ。私も夏の稽古のときは酷いものですから」
社交辞令ではなく本心から気にしていなかった。むしろ、真夏に汗だくになりながら集中して芸事に打ち込む姿は誇らしいものだと思っていた。
「わしはスイカを冷やしてこよう。すぐに政と、あとの二人も来るだろうから待っていなさい」
そう言って、大きなスイカをひょいと持ち上げるとお祖父様は庭のほうに消えていった。
一人になって、蝉の声が大きく聞こえる。
重厚な日本家屋の匂い、そして陶器の湯のみに入った冷たいお茶の香り、夏はあまり好きではないけれど、今この空間は好きだった。
「ごめんごめん、待たせた! あれ、じいちゃんは?」
答えようとすると、別の声が入った。
「庭でスイカを冷やしてるんだろ」
低く、それでいて澄んだ声。
政の後ろから現れたその人は写真で見た、あの男の子だった。
そして更にその後ろからひょこっと顔を出したのはこれまた美しい西洋風の顔立ちの少年だった。少し高い声で、彼は嬉しそうに声をあげる。
「スイカがあるんですか⁉ 縁側で食べましょうよ! 僕、縁側で食べるの好きなんですよ!」
『蘭ちゃん』とは対象的な明るい男の子。彼のことは聞いたことがない。おそらく政の友達ではなく、蘭ちゃんの友達なのだろう。
政は彼らを私の向かいの席に促し、三人分の緑茶を注ぎながら話しはじめる。
「蘭ちゃんの方が前にも話しとったやろ。一緒に弓道やっててん」
コトン、と彼の前に湯呑をおく。
「ほんでもって、その隣の一信くんが蘭ちゃんが悩んどった──」
ここで政は言葉を切り、一度二人の方を見た。すぐに二人が笑顔を返す。蘭ちゃんの方は控えめにほほえみ、一信くんと呼ばれた子はパッと明るく笑った。それで何かしらを了承したらしかった。なんだろう、と思うとすぐにそれは政の口から明かされる。
「二人は、恋人なんや。前に言うとったやろ。蘭ちゃんが恋愛でちょお悩んどってな。相談にのってたやつ。今は無事にっちゅうか、上手くいってなぁ」
「──……恋人?」
私は思わず顔色を無くした。すぐに目の前の可愛らしい男の子がまるで違う姿に見える。
「男、どうしでしょう」
加矢の言葉に政は驚いてガチャンと音を立ててやかんを半ば落とすように机に置いた。政が何かを言おうと息を吸い込んだのを遮るように、声を上げたのは大人しそうな方の彼。
けれどもそれは加矢に向けられたものではなく、隣に座る恋人と、暗に政に対しても伝えていた。
「一信、帰るぞ」
動揺しながらも、恋人に従って席を立とうとする。それを、政がとめた。
「こんまま帰るんは、あかんやろ。なぁなぁにして聞かんかったことには出来ん」
けれども、彼は一歩も引かずに答えた。
「同性愛を嫌悪することは罪ではない。そして、俺は俺のせいでお前と恋人の仲が悪くなるのはごめんだ」
冷ややかな声で、彼は決然と告げる。けれどもこの状況に一番に耐えられなくなったのは、他ならぬ加矢であった。
「私が帰ればいい話でしょ」
立ち上がる彼女に政の表情が更にこわばる。
「男同士で付き合ってるなんて、信じられない」
そう言い捨てて出ていく彼女に対し、政は明らかに怒っていた。ともかく彼女を追いかけて謝罪をさせねばと思っていた。彼にとって、大切な友人である蘭を傷つけるような発言は許せなかったし、心の何処かで加矢なら二人の関係を自然に受け入れて祝福してくれるだろうと思っていただけにこの状況が信じられない気持ちすらあった。
居間を出ていこうとする政の腕を、蘭が引き戻す。
それはひどく優しい顔で、ともすれば、悲しげな目で。
「あの人を責めるな」
政は目を見開いて、はっきりと言い返す。
「どんなに嫌いでも、傷つけてえぇ理由はない」
「そんなことはない。俺たちの存在が彼女を傷つけてしまったんだ。仕方のないことだ」
「……なにを、言うとんのや」
政には、ひどく自己犠牲的に聞こえるその発言すら、腹立たしかった。けれども蘭は彼の手を離してから、穏やかな声で言う。
「怒るのも、責めるのも、彼女の話を聞いてからにしろ。お前が彼女を信じているのなら、なおのこと」
政はその言葉になにも返さず、部屋を出ていった。
【本当のもの】
中学生のころ、父親は家を出ていった、しばらくして離婚の手続きをするための書類が届き、母が泣きながらその紙を埋めていくのを見ていた。昨日まで当然のようにあった家庭というものが一瞬にして崩れていった。
だというのに、母は離婚の理由を何一つ教えてくれなかった。
優しい母と、理性的で穏やかな父は子どもから見ても仲がよく、離婚の原因なんて思いつかない。それに、話し合いもほとんど無いまま母親が離婚を受け入れているのがなにより信じられなかった。
私は母に黙ってなんとか父に会えないかと思い、学校をサボって父の会社の前で一日中待ち伏せをしてやろうと思った。
すると昼になる前に父が出てきて、熱中症にでもなったららどうするんだと少し慌てて言った。どうやら会社の窓から見えていたらしかった。
「どこか店の中にはいろう」
「……仕事は?」
父が仕事を終えた後に捕まえようと思って待っていただけに、心配になって聞くと、彼は少し驚いたように大丈夫だよと言った。
「好きなものを頼みなさい」
テーブルごとに仕切られた少し高そうなカフェだった。
けれども私は店員さんが水を置き、立ち去るや否や父を問い詰めた。
「どうして離婚したの。父さんが出ていったあと、ずっと、母さん泣いてたのよ! でも何も話してくれないし。このままじゃ私納得できない。ちゃんと話し合いもしないでいきなり離婚だなんて!」
「……ごめんな。加矢」
父は悲しそうに、無理矢理に微笑んで、なんとか涙をこらえながら話した。
「全部、父さんのせいなんだ。母さんを騙して結婚して、でも、結局なにもかもばれてしまった」
ばれる? 何が? 騙してたって? 困惑する私に父は一言、告げた。
「父さんは、男の人が好きなんだ」
その後のことは覚えていない。父に対して何かを言ったのか、それともすぐに店を飛び出してしまったのか。気がついたら家に帰っていて、母が心配して私の名前を幾度も呼んだことだけぼんやりと思い出せる。
──政は最後まで表情を変えずに私の話を聞いていた。
人通りのない、無駄に広い道の真ん中でぎりぎり木陰に隠れて、暑くはなかった。でも汗と涙が止まらなかった。
「あの男は、ずっと嘘をついてたのよ! 母さんのことも私のこともこれっぽちも愛してないくせに! 平気な顔して、ずっと、ずっと……!」
倒れないように、足を踏ん張りながら訴えた。
「自分のためだけに母さんを利用して、さも自分はまともです、正常な人間ですって思われるために! そのために母さんに私を産ませたのよ!」
加矢は、父親が世間体のために母親と結婚したのだと成長して様々なことを知るうちに理解した。そして同時に父親が性指向を偽らなければ自分は生まれなかった存在だと気づいた。
母を騙した男が許せない気持ちがあった。だから父親に似た優しげな男は嫌いだったし、同性愛者はもっと嫌いだった。
でもあの二人の少年を傷つけるために言葉を吐き捨てたのは、同性愛者への嫌悪だけではなかった。
恐ろしかったのだ。男同士で付き合っていて堂々としている人間は、自分が生まれなかった未来を暗示しているようで。
「愛は、目に見えん」
政がぽつりと言った。
「俺は、加矢の父ちゃんのことは知らんけど、加矢のことはそれなりに知っとるつもりや。加矢はいつも色んなことに気ぃつくし、困ってる人とか、落ち込んどる人とか、パッと助けてあげられるんは、ほんまにすごいと思っとる」
「……何が言いたいの?」
遠回しな言葉に苛立ちながら睨み返すと、彼は恐ろしいことを言った。
「ほんまに、父ちゃんは愛情のない人やったんか?」
頭の中が真っ白に燃えるほど熱かった。意味が分からなかった。
「ほんまに父ちゃんが愛情なかったら、加矢も、加矢の母ちゃんも気づいたんとちゃうんかな。気づかへんかったてことは、父ちゃんは、ちゃんと加矢のこと大事にしとったと違う?」
「ち、ちがう! 違う‼ あいつは、愛して無くてもセックスできる最低な男だったのよ!」
金切り声をあげる加矢とは対照的に、政は冷たく返した。
「そら、出来ると思うで。誰でも。生理現象やろ」
呆然とする加矢に構わず言う。
「そういうことが出来るかどうかと、愛情は関係ないやろ」
普段の物言いからは想像もできないほど冷静であまりにも現実的な考え方に、怖いと思った。けれど、その言葉に、すがりたいとも思ってしまった。
ぐらぐらと、あしもとが揺れている。
ちがう、揺れているのは私。
父さんが、母さんを少なくとも人として大切に思っていて
そして私という子どもが生まれてきたことを、ほんの僅かでも喜んでいたのなら。
「父さんも、苦しかったのかしら」
──倒れた加矢を抱きとめて、祖父の家まで運んだ。多感な時期に受けたショックと長い間抱えてきた嫌悪感はそう簡単に無くならないだろう。無理に受け入れて欲しいとも思っていない。
けれど、強く優しい彼女ならば目覚めたときに介抱を手伝ってくれた二人の友人に──
「ありがとう」
【『ホモフォビア』終】

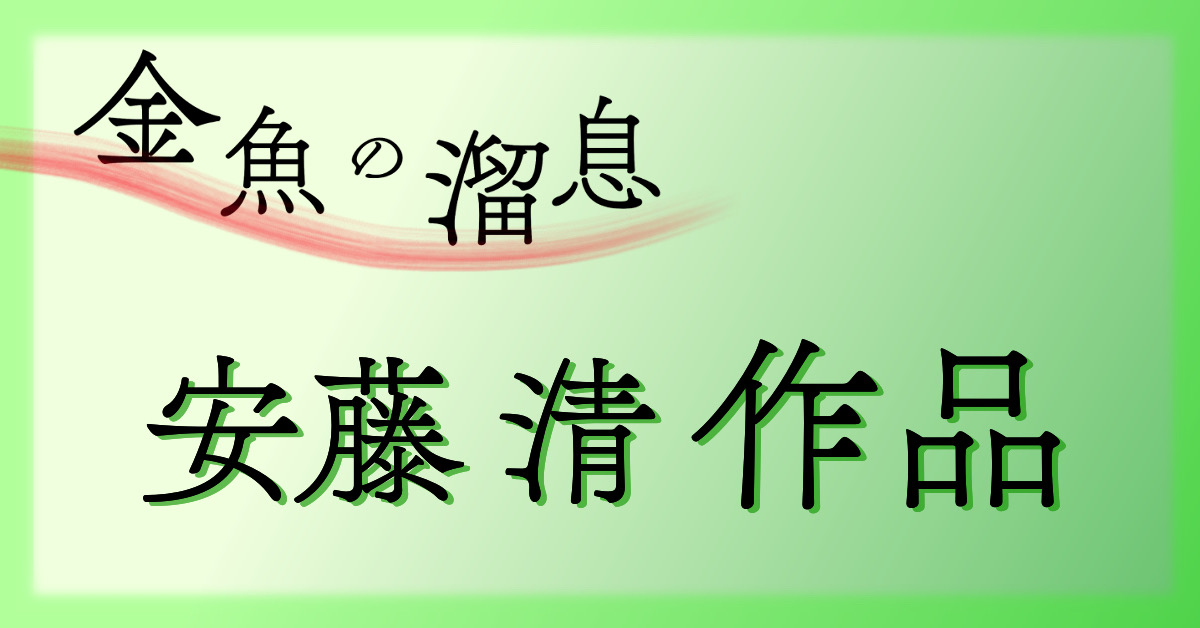

コメント