掲載日 2024/12/09
読了目安 45分
【あらすじ】
殺し屋の男が疲れ切った顔をした女に助けられる。男は自分が殺し屋であることを知られてしまった以上、何かしらの対処をしなければならないが、出来ないまま助けてくれた女の家を去る。しかし、再び仕事で怪我をしたところ女に出くわしまた助けられてしまう。
お人好しのようだが、あまりにも愛想の無い女が何を考えているのか分からず、けれども助けられた以上、恩を感じてしまう男はある日、女が拐われるところを見てしまい……。
『どうぞ、私を殺して』
【1】
帰り道、あたりはもう真っ暗でけれども街灯の明かりがあるから、いつも通り近道をして公園の中にある階段を下りていたとき彼女の視界に人影が入った。
ふたつ。そのふたつは距離があって知り合い同士という感じではなかったけれど、一方はまるで後をつけるように歩いている人を追っていた。追われている方は気づいていない……?
なんだろう、と思ったとき追われていた方が気づいて後ろを振り返った。
驚いた様子、一瞬の会話、あぁ知り合いだったのかと思った次の瞬間、追っていた方、が、見慣れない奇妙な動きをして、彼女は思わず息を呑んだ。
振り返ったほう、が、倒れたからだ。パンッと乾いた音が一瞬遅れて耳に響く、映画のように逃げていく男と倒れて動かない男。
彼女は目の前で起きたことが理解できず階段の手摺に縋りつきながら、やっと立ち上がると倒れている男のところへ駆け寄った。
【2】
「うっ……」
起き上がると、まず横腹が痛んだ。
「無理に動かないほうがよろしいですよ」
部屋の隅で洗濯物を畳んでいたらしい女が顔を上げた。長い黒髪に疲れ切った表情をした陰気な女。
「……あんたが助けてくれたのか」
「えぇ。救急車を呼ぼうかと思ったのですが、応急処置の時に、どうやら呼ばれては困りそうな物をお持ちのようでしたから」
なるほど。それでわざわざ自分の家に運び入れてくれたわけだ。たしかに、呼ばれちゃまずい身の上なのは間違いない。なにせ銃刀法にはしっかりと違反しているしそれだけではなく、身元なんかも大体調べられるとまずいものしか出てこない。表の医者にはまずかかれない立場だ。
「ありがとな」
ひとまず礼を言うと、そっけない返事が返ってくる。
「いえ……仕事柄、ほっておくわけにもいかなかっただけなので」
「……人命救助のお仕事を?」
助けた割には、こちらを見ることもしない女の様子に少しうがった言い方になる。
「一応、病院で働いております」
淡々と、家事を続けながら女は言った。
冷めた看護婦もいたものだ。しかしどおりで銃傷を見て冷静に手当なんてできるはずだ。心なしか包帯の巻き方もキレイな気がする。俺とは正反対の職業人ってわけ。
俺は知らずため息をつきながらなんとか立ち上がる。
「……起き上がって大丈夫ですか。痛むでしょう」
「あぁ。ま、痛いのには慣れてるからな」
なんとかベッド脇に畳んであった自分の上着を着込む。
「お帰りになりますか」
「あぁ」
「では、玄関へ案内いたします」
言って、立ち上がるために膝の上にあった洗濯物を横に置いた女に、ひやりと冷たい銃口が向けられた。女は一瞬またたきをして、けれどもそれ以上の驚きはなく男を見上げる。
「救急車を呼ばないほうが良いとは考えたけど、自分がこういう目に遭うってことは考えなかったのか?」
「……いいえ。考えました」
明らかに一般の職業の人ではない人を助けて、それを仇で返されることも、口封じのために殺される危険があることも理解した上で女は男を助けた。
「そうか。じゃあ随分と大変な自己犠牲だな。それとも看護婦なんてやってるやつはそれが普通なのか?」
「そういうわけでは無いと思いますが……。まぁ、殺されるのもまた一興と思いまして」
濃いクマが目立つ女は少し微笑んだ。疲れたように。そうして言った。
「もう、いいかと思って。……毎日、働いて、喜ばれたことより、失敗したことのほうがずっと覚えています。感謝されることなんてほとんどなくて、同僚には嫌味を言われて、どうでもいい嫌がらせの一言がずっと気になって。でも生きるのをやめることも出来なくて、一所懸命、他人が生きるのを手助けしながら毎日思っているんです。死にたいなって」
女は本当に疲れていた。
「たいして他人から求められてもいない私が、平凡な毎日を死なないだけの私が、ある日突然、自分の部屋で撃たれて死んでいたら、少し面白いと思いませんか」
そう言って、それは目を伏せた。どうせなら額の真ん中を撃ち抜かれるのが一番それらしくて良いと思ったのだろう。
「どうぞ」
けれども、次に目を開けたとき女の前から銃口は無くなっていた。
「お帰りになるんですか」
もはや後ろ姿になった、くすんだ緑色のジャケットを見ながら尋ねる。
返事は帰ってこない。かわりにバンッと乱暴にドアを閉める音がした。
【3】
怪しい男を助けたのが先月、あっという間に一ヶ月が過ぎた。
「5月とはいえ、まだ寒いですね」
女は路地裏の暗闇に立って買い物帰りのネギをバッグから飛び出させて尋ねる。
「ゴミ袋の上で眠るには早い時期だと思いますけれど」
「好きで寝てるんじゃねぇ」
不服そうな声で返事がある。
「自分で歩いてくださいね。あなた、重いので」
よろよろと起き上がった男に肩をかしてやる。やはり重かった。前回のように出血はしていなかったが、そのかわり顔は挫傷していたし、どうやら左足を怪我しているようで、跛行状態だった。
「怪我するのが趣味なんでしょうか」
「嫌味なやつ!」
【4】
「あんたこそ、いつもこんな事してんのか」
この間と同じ、くすんだ緑色のジャケットが女の白く柔らかい清潔なベッドの上に沈む。
その怪我人は斜めに寝転んで、もう起き上がる気力はなさそうだった。
「こんなことって?」
少し大きな救急セットらしきものを取ってきた女は無表情のまま男の側にひざまずいて左足に触れた。
「イッッ!」
「折れてはいませんね。腫れていますからヒビくらいは入っているかも知れません」
「……そうかい」
普段、組織の後輩やなんかにこんなふうに触られたら思わずキレたくなるのに、この女はあまりにも静かに言うものだからこっちまで調子が狂ってくる。
いや、そんなことはどうだって良い。
「おい、だからいつもこんなことをしてるのか?」
「服、切っても良いですか?」
「良くねぇよ! そこまで本格的な治療してくんなくてもいんだよ。ちょっと休ませてくれれば十分だから」
まるで人の話を聞いていない。怪我の治療しか頭に無いんだろうかこの女は。
「では応急処置だけしておきますね。お顔の方も」
服の上から包帯をしっかりと巻き付けられた後、顔を真っ白いタオルで拭かれて丁寧に傷口を消毒される。
「こんなもんほっといても治るだろ」
「手当をしたほうが、放っておくより早く綺麗に治るものですよ」
「そうかねぇ」
また嫌味な調子で言ってしまった。どうにもこの薄幸な顔をした無防備な女を見ているといらついてくる。
「ほら、これで良い」
手当が終わった女は救急セットをしまいに部屋から消える。
きれいな部屋だ。白と淡い緑を基調にした落ち着いた家具に、広くも狭くもない一人暮らしの女の部屋。整えられていて、俺の数週間捨ててないゴミ袋がほったらかしてある部屋とはずいぶん違う。それになんだかいい匂いもする。ゴミがないとこんな匂いがするものなのか。
「痛み止め、市販のだけどないよりましでしょう。飲みますよね。水を取ってきますけど他になにか、胃に入れますか。大したものは無いけれど」
「……ちょっとこっちに来てくれないか」
女はどうしたのだろうというように、何も持たないまま俺の方まで歩いてくる。
「もうちょっと」
言いながら、俺の言葉を聞こうとかがむ女の肩に手を伸ばす。そのまま、一瞬、引っ張れば簡単にそれは俺の下に組み伏せられた。
「なにがしたいんですか?」
ベッドに押し倒されても平然と、女はクマのひどい目で見上げてくる。
「なに、いつもこんなふうに得体の知れない男を助けて回ってるのかと思ってな。流石に警戒心がなさすぎじゃないのか?」
俺がけが人とはいえど、こんなに簡単に抑えつけられるくらいには、ひ弱な女だ。危機感が無いのか、それとも自分が女という自覚が無いのか。
「以前も似たようなことを申し上げた気がしますが」
女は一言前置きをすると、呆れたように告げた。
「どうぞ」
短く。疲れ切ったように。
「警戒心が無いのではなく、警戒するつもりが無いのですよ。あなたの気が変わって私を殺すつもりになろうが、レイプしたいと思おうが、大した違いはありませんので」
男はあっけに取られて思わず女の上からどいた。
「気はすみましたか? では、痛み止めを持ってきますから」
女は肩から少しずれたカーディガンを直しながら立ち上がって、何事もなかったかのように俺から背を向ける。
けれども、部屋を出ていく時、ふいに振り返って思い出したように言った。
「あぁ、そうそう。私は別に誰でも部屋に入れているわけではありませんし、不特定多数の男性と関係を持っているわけでもありませんから。……もう、そういうのは疲れてしまったもので」
もう疲れてしまったということは。かつてはこの陰気な女も、恋に溺れていたことがあったのだろうか。そういうことから縁遠くなるには、まだずいぶん若いような気もするが。しかし、名も知らない女の人生を邪推するより先に、左足の痛みが本格的になってきたことが目下の問題であろう。
【5】
病院からの帰り道、医師免許のない医者に法外な、本当にそれは法外な値段を取られて、それでもやっと怪我のない体で歩けるのが嬉しくて、包帯のない足を見て身軽だなと思いながら歩く夜。
コンビニでビールを買って、人気のない坂道を下っていたらそれは見えた。
高架線の下、フェンスの向こう側。
白いワゴン車にはナンバープレートが無い。
マスクをした男たちと──髪の長い女……!
ガシャンッとビールの缶がフェンスにぶつかりながら俺は身を乗り出した。
いや、まて助けるのか? やっと怪我が治ったのに。死にたがっている変な女を助けるためにまた病院通いか。
そもそも、あの女が危ないことに首を突っ込んでくるのが悪いだろう。しかも、危機感もなくこんな夜中に出歩いたりなんかして。
第一、本当はとうに殺されているはずだった。俺が最初に会った時に殺さなければいけなかった! なにせ、あの女は目撃者なのだから。それを思えば、あの女がこれからどうなろうと知ったことではない。むしろ俺の変わりに殺してくれれば手間が省けてありがたいというものだ。
いやしかし、今日まで誰にも何も言わずにいるのだから、わざわざ殺す必要もないんじゃないか?
いやでも、俺がわざわざ助ける理由だって、二回も助けられたくらしかないじゃないか。
そう、二回も……。
──坂道に置いていかれたビニール袋の中には俺の大事な224円たちが入っている。走り去った白いワゴン車を追いかけるのに、ビールはあんまり重くて邪魔だった。
【6】
全力疾走は仕事柄めずらしくはないのだが、オペレートもなしに車の行き先を予測しながら走るのは流石にめずらしい。頭も身体も重労働だ。このへんの地理と、そういうことをするのに向いてそうな建物なら一通り頭に入ってはいるものの、武器は心もとないし、果たして無計画に突っ込んでどこまでやれるか。しかし用意している時間はない。
そう思うとそれは角を曲がった瞬間とびだして来た。正確には、俺が走っていたので飛び出したように感じた。けれども相手は律儀に謝りながらこちらを見上げる。
「──おまえ!」
見上げた女は、びっくりしながら少しだけ安心したように笑っていた。
「すごい勢いで飛び出して来たから驚きました。お仕事中だったんですか? 邪魔してしまって申し訳ありません。怪我は無いのでお気になさらず」
スカートについた汚れを払ってから荷物を持ち直して、あっという間に驚いた表情も消えてそう言った。理解は出来ないながら安堵した。けれど、ふと気づく。女の上着を見て。
「おまえ、ボタンかけちがえてるぞ」
薄手の上着は妙な方向によれている。
「え……?」
女が確認するよりも先に俺の手は薄い上着をひっつかんでいた。
ぶちぶちっ、と音をさせながら無理な勢いで開かれたボタンがはずれる。
あらわになった白い鎖骨と中に着ていた桃色のシャツ。薄暗い街灯の下でも、なんのアトもないらしいことは分かった。
思わずホッと息をつくと、女の胸元に注いでいた目線のちょうどすこし上からため息をつくための息を吸う気配があった。顔をあげると、女は案の定ため息をひとつ。
「どうして走ってらしたんです」
「え……どうして、って……」
「そんなに血相を変えて、こんな小さな掛け違いを気にするのは無理があると思いませんか。私の態度からでは、異変は分からなかったでしょう?」
どこか不気味に、女は薄く笑いながら首をかしげた。
「……あぁ。びっくりするほど、いつも通りだったな。拉致されたとは思えない落ち着きだよ」
「連れ去られたところをご覧になって、そこから追いかけて来てくれたんですか。それで走っていて、私にぶつかったんですね」
どこか苛立たしげにも見える、いつもより早口な様子でつらつらと推理を述べた。
「そう、だよ……」
「ご心配おかけしまして。私はご覧の通り何事もありませんので安心してください」
そう言って平然と立ち去ろうとするのを見送りかけてあわてて引き止める。
「おい、ちょっ、何事もありませんってことはないだろ! 怪我はなさそうだが……抵抗しなかったんだろ? それは賢い選択かも知れないが、何をされ、あ、いや……」
それを言わせるのは可哀想だ……かといってこのまま引き下がっていいものか……。
「勘違いなさってるようですけど、少しお話ししただけで皆さんご理解くださったので本当になにもされていませんよ。ボタンがズレていたのは車にのせられた時に少々乱暴だったので上着が乱れただけです。暗い中で止め直したのでズレてしまったんです。あなたが想像なさってるようなことはありませんから」
淡々と説明されても、本当にあの状況から何事もなく帰ってくるなんてことがあるだろうか。
「信用できないなら、お調べになりますか」
女はあやしく笑った。俺がそれをしないと当然のように思っているのだろう。だから俺の返事を待つこともなく、軽く頭を下げると「では、また」と言って立ち去った。
今から走って戻れば、まだあの置き去りになったビールは残っているだろうか。
残っていたとしても、飲む気にはとてもなれそうにない。
俺は、女のことを信じられなかった。
【7】
「加瀬、次の仕事だがお前には新しく出来る病院に行ってもらう」
妙に威圧感のある、サングラスを絶対に外さない上司からそう言われ、病院の情報が書かれている書類を渡される。
「これって……潜入、ではない、ということですか?」
いつもなら用意された偽名やその他、設定が書かれているが今回はそれらがなく、勤め先の病院だけが書かれており、ずいぶんと情報がない。
「そうだ。その病院はいわゆる裏、専門だ。ただ、院長である医者は医師免許をもってる正規の医者だ。お前にはその院長の警護をしてもらう」
「わっかりましたけど、正規の医者がなんで闇医者なんかするんです? 変じゃありません?」
いまいち納得のいかない辞令だ。命令である以上文句を言える立場ではないが。
「行けば分かる。さっさと挨拶してこい」
「っす」
腑に落ちないまま書類を見ながら部屋を出ようとすると、後ろから一言足された。
「お前、昨日の晩飯なに食った?」
「はぁ? 昨日は……チンジャオあっためて食いました」
「そうか。俺も今日はチンジャオロースにしようかな」
「あーいんじゃないすか」
意味の分からない会話に意味はなく、そのまま俺は部屋を出た。
あの人の天然にイチイチつきあう神経は持ち合わせていない。
【8】
ぴんぽーん、と古そうな建物のインターホンを鳴らす。おそらく付け替えたばかりであろう看板には『柳病院』の文字。柳の字だけ汚れていないからそれ以外は前に使われていたのをそのままなんだろうな。病院でも居抜き物件というのはありなのか。あまり気にしてみたことはないが、まぁイチから建てるより早いだろう。
それは良いにしても、出てこない。
もう一度インターホンを鳴らす。今度はザザッと音がはいる。
[はい。加瀬様ですね。今そちら開けましたので入ってきてください]
どうやらもう看護婦はいるらしい。
見かけによらずハイテクな玄関を通過して、キョロキョロと間取りを確認しながら進んでいくとすぐ先に気配のある部屋がひとつ。
「すみません。加瀬ですが」
そう挨拶した先には、白衣を着た女がいた。
「あぁ。こんにちは。片付けで手が離せなくて出迎えも出来ず申し訳ありませんでした。私がこちらの病院の医院長を勤めることになりました柳かすみです」
「あ、あんた……!」
「早速ですみませんが、こちらのダンボールに入っている書類を棚に移すのを手伝ってもらえますか?」
俺が驚くのはそっちのけで、さくさくと片付けを進めようとする女に思わず声が大きくなる。
「あんたこんなとこで何やってんだ! 医者って、いや、この際こまかいことはどうでもいい。この病院を開くのに、なんの力を借りたか分かってんのか!」
「どういう意味でしょうか」
書類を引っ張り出しながら、片付ける手を止める気配はない。
「『裏』の息がかかった病院をやるってのがどういうことか分かってんのかっつてんだよ!」
「どこにいても私がやることは変わりませんし、これで三度は申し上げているかと思いますが、私は私がどうなっても構わないので、この仕事が危険なのはどうでも良いことなのですよ。それより、もう同僚の男どもに嫌味を言われなくて済むと思うと気が楽です」
「同僚はいなくっても患者はろくなもんじゃねぇだろうが!」
「病人や怪我人なんて似たようなものでしょう。患者ではない人が来た時はよろしく頼みますよ。そのためにあなたを雇っているのですから」
淡々と、本当に淡々と。作業をしながら言って、疲れたようにため息を一つついた。けれど、そのため息は、いつもより少し軽やかに思えた。
女にとっては命の危険よりも、心労のほうが重かったらしい。
「……、……こっちのダンボールも、片付けるんですか、先生」
【9】
病院が開院して、まだひと月も経たないうちから患者はチラホラとやってきた。ほとんど看板もなく、宣伝もなにひとつしていないが先生は暇なくらいが丁度いいと言ってダンボールで届いた業務用の消毒液を面倒くさそうにしまっていた。
いよいよ暇だと、先生は俺に応急処置の手ほどきをしはじめる。最近は日に二、三人くる患者の相手をして、それ以外の時間は医療の知識を教わるか、模型を使ってそれらの実践練習をするか……。あとは、たまに先生の書類整理を手伝ったり、俺の武器の手入れを先生がながめていたりもする。
「拳銃って案外パーツが多いんですね」
キィと椅子を鳴らしながら退屈そうに言われる。
「まぁ物によりますけどね」
「そういうものですか」
「興味があるなら今度、撃ってみますか」
どうせ断られるだろうと思ったが返事は意外なものだった。
「いえ、撃ったことはありますので。下手なのであまり楽しくもありませんでしたけれど」
俺は思わずギョッとして手元から顔をあげる。
「撃ったことが!?」
「えぇ。ロスに研修で行った時に。折角なので友人と行ってみたんですよ。射撃場」
平然と言っているが、もしかしてこの先生は実は結構ちゃんとした偉い先生だったりするのだろうか? 医者というのはそんなにポンポン海外に行くものなのだろうか。
「ていうか……先生っていま歳いくつなんですか?」
医大は卒業に時間がかかるらしい。医師免許をとってそんな研修まで行ったらそれだけで何年かかるんだろうか。
「私は今年で32です」
年下か……いや、見た目からしてそうだろうとは思っていたのだが……。
「あなたは?」
「あっ、俺は36になります」
「ふぅん。そうなんですね」
心底どうでも良さそうに相槌をうつと、女──ではなく、先生は会話に飽きたのか書類整理に戻っていった。
先生はいつも何を考えているか分からない。
表情も変わらなければ声の抑揚もほとんどなく、驚くと少しだけ動きが止まるらしいことには気づいたが、それ以外の感情は見えない。大体いつも疲れたようにため息をついているか、明らかに愛想笑いだと分かる笑顔を患者に向けてたまに浮かべるくらいだ。
あまりにも冷静な対応に、患者は威圧感を通り越して尊敬をし始める始末。この間はどなり散らしていた怪我人にまったく表情を変えないまま淡々と説明をし続けるので患者の方もなんだか静かになってしまって最後には頭を下げて礼を言っていたのだから、俺まで先生は案外この業界に向いているのかもしれないと思い始めている。
けれど、本当ならこんないつ命を狙われるか分からない世界にいていい人じゃない。初めて病院に来た日は思わず怒鳴ってしまったが、考えてみればすぐに分かる話で、先生は黙っているが、白いワゴン車に連れて行かれた日になにか取引をしたのだろう。そしてそのきっかけはおそらく俺と関わったせいだ。
だから俺は、先生に足を洗ってもらおうなどと思ったところで、それを口に出せる立場ではない。先生とてそれが出来るならばしているだろう。所為、俺のせいでこの業界に入り、そして抜け出す手段はないというのが現状だ。
「……俺を恨んでもおかしくないはずなのにな」
俺に関わらなければ今も心労を積もらせながらも普通の病院で普通の医者として働いていたはずなんだから。
「恨んでませんよ」
ハッとして振り返ると、いつの間にか先生が立っていた。
「気配も確かめず気を抜いて独り言とは、珍しいですね」
言いながら、先生は両手に持った湯呑を机の上に置いた。
「どうぞ」
「……あ、りがとうございます」
書類整理に戻ったのではなく、この緑茶を淹れるために席を立ったらしい。わからない。この人のことが分からない。
「あの、……さっ、きのはなしぃなんですけどぉ……」
緊張してびみょうに間延びした喋り方になってしまう。が、先生は特に気にすることもなく視線だけをこちらに向ける。
「……言っちゃあなんですけど、俺のせい、っすよねぇ」
「随分しおらしくなりましたね。最初に銃を向けてきた時はまさに殺し屋という感じで怖かったものですけれど」
そう言って、湯呑に近づいた口元は少しだけ笑っていた。
「怖かったって、全然そんなふうには見えませんでしたけど? そもそも、俺はホントは脅したりとか、そういうの得意じゃないんですよ」
「人殺しは平気なのに」
「それは……」
紛れもない事実なのに、この人に『人殺し』と言われるとその言葉がどうしようもなく鋭く聞こえる。
「それは?」
「……生きてる人間のが、怖いじゃないですか。殺す時は、別に、コミニュケーションなんて取らなくていいし、普通に? ってか、まぁバレないように気をつけて、仕事して終わりですよ」
「じゃあ私を殺さないで見逃してくれたのは随分と面倒だったでしょう」
実を言うと殺さないといけなかった。と伝えるのは無意味だろう。
「そうっすね殺す方が簡単だったかもしれないです」
先生は珍しく優しそうに笑った。
「私は運が良かったんですね」
もしかしたら、先生はすべて気づいているのかもしれない。
本当は先生を殺す必要があったことも、それをしなかったことで先生が今の仕事を強いられていることはもちろん。
俺が、人を殺し逃したのはこれが初めてではないことすら。
だから、人の命を救って生きている先生とは正反対のところにいるのに、まるで蔑んだりしないで、恨むことすらしないでいてくれるのかもしれない。
【10】
「なんで黙ってたの……!」
いつもより上ずった声でそう詰め寄る女がいた。
「言ったらお前、怒るだろ」
面倒くさそうに男が答える。長身で顔立ちも整った、白衣を着た男。
よく見ればふたりとも白衣を着ていた。
「当たり前でしょう……! 知ってたら付き合わなかった。二股なんて、……最低」
女は蔑みを込めて男をにらみつけるが、まるで意に介した様子はなく薄ら笑いのままその発言を訂正した。
「二股っていうか、何人か分かんないけど。まぁ浮気してたのは悪かったよ。でも珍しくもないじゃん。ただでさえ俺らモテるしさ。お前も同じ業界にいたら分かってるだろ?」
「他の医者が浮気してるのは知ってるわよ! あんたが浮気してるのは知らなかったって言ってんの!」
消灯後の院内の一室で話す二人の様子は対称的だった。
「まぁさ、本命はお前だから。やっぱり話してて会話のレベルについてこれんのはお前だけだし、仕事でも頼りになるし。他の子とは別れるから許してくれよ」
「許すわけ無いでしょう。私は二度とあなたを信じられなくなったんだから」
男は内心、少し焦った。
「二度となんてそんな大袈裟なこと言わないでくれよ。悪かったって。これからはお前ひとりだけにするから」
女の手に触れてわざとらしく甘えてみせる。
「お願いだよ、かすみ」
優しい声で名前を呼べば、この鉄面皮の女は絆されるだろうと思った。なにせ、美人なのに性格のキツさと感情表現の乏しさのあまり周囲から距離を取られているような可哀想な奴で、女医という立場も相まって頭の良すぎる女は恋愛経験も少なく、付き合うまでも簡単だった。
「な、信じてくれよ。もうしないから」
常套句、でもこの寂しくて優秀な女は騙されるだろう。
「いいえ、どうぞ」
女は短く言った。男は言葉の意味が分からず一瞬の間があったので、丁寧に付け足した。
「どうぞお好きなだけ女の人と遊んでください。もう私には関係のないことだから」
赤くなった目で男を一瞥だけすると、女はくるりと背を向けた。
そのまま部屋を出て、静かに扉が閉まってから男はやっと言われたことの意味を理解した。手遅れになってから急に現実味が降ってきて、部屋の中で一人、頭をかかえる。
「え、俺、振られたのか?」
男は、彼女のことを愛していなかった訳では無い。
本命だと言ったのは真実で、大事に思ってもいたのだ。それよりも、他の女と遊ぶことを軽く見すぎていた。これは遊びだから、たまの気分転換くらい大目に見てくれるだろう。なにせ彼女も俺のことが好きだから。
「今なら、今ならまだ……」
男はボソボソと呟きながら部屋を出る。
【11】
件名:これで最後にする
本文:かすみ、お願いだ。今夜もう一度だけ話をさせてくれ。
そしたらもう電話もメールもしない。このまま終わりたくないんだ。
今日の十一時にいつもの資料室で待ってる。
「当直は真面目にやりなさいよ……」
呆れながら、携帯を閉じる。
このままこれを見ないふりをしてしまうのは簡単だ。でも、私だって未練が無いわけではない。彼が女性に人気なのは知っていたし、告白されたときは信じられない気持ちだった。
今の病院に配属になったばかりのとき、緊張してミスをしてしまった時も他の男には、やっぱり女の医者なんてと言われたりしたものだが、彼はそんな中で顔色を変えずにフォローしてくれたし、別け隔てなく優しい人だと思った。
好きになるのに、時間はかからなかった。
だから彼から告白された時は本当に嬉しかったし、彼に浮気をされていると知った時も、本当に悲しかった。
これで終わりなんて、と思う気持ちは同じだ。でも、何度も私を愛してると言った口で、優しく触れてくれた手で、平然と他の女性にも同じことをしていたのだろうかと思うと、もう彼がどんなに言葉を尽くしてくれたとて、信じることはできない。
でも。
最後、最後に、一度だけ……。
そう思って。
十一時を少し過ぎてからあの人の待つ部屋へ行った。
そこで見た。愛しい人の業。
「待ってくれ! じょ、冗談だろ!?」
叫ぶ彼の声が聞こえて、驚いて明りの漏れている部屋の方へ走るとパンッと乾いた音が聞こえた。
灰色の床に散った赤い──。
「見られたか」
振り返った男は、マスクをして帽子を目深に被っていた。黒く、重い銃を右手に。くすんだ緑色のジャケットには、目立たないがよく見れば返り血が飛んでいる。
「悪いが、目撃者は殺すことになってる」
向けられた銃口に、私は何も出来なかった。目の前で殺された恋人と、突然目の前に迫った自分の死に頭が働かない。
立っていられなくなって、壁を背に、そのままずるずると座り込む。
ここで、死ぬのか。恋人の浮気のせいで、最後に話そうと思ったことで。そんなことで。そんな、私を裏切った男のせいで死ぬのか。
引き金にかけられた手はなかなか動かなかった。床に座り込んだ女の額を正確に狙いながら。両目を見開いて銃口をにらみつける女を撃ち抜けずにいる。まるでひどく悔しそうとも思えるその目つき。涙をこぼしながら、それでも瞬きすらせず生気あふれる目をした女が、これから死ぬとは思えなかった。
「……ここで、俺を見たことを誰にも言わないと誓うか」
尋ねると、女は静かに瞬きをひとつした。
俺は、女を信じることにした。
【12】
怪しい組織の力を借りて開業医になってからはや一ヶ月。以前より早い時間に帰れることが増えたが、今日は少し大き目の手術が救急で入ったため遅くなった。
今から帰って食事を作るのも面倒なので珍しく外食をすることにしたのだけれど、結局落ち着かなくて急いで食べて出てきてしまった……。
女はふらふらと駅から少し離れた飲食店街を歩く。
この時間になると、すでに何軒かはしごした後らしい集団もチラホラと見かける。サラリーマンらしき人たち、年齢層がバラバラだけど仲が良さそうな人たち、若者ばかりの人たちもいる。みんな生きて、生活していて、それが同じように顔を赤くして千鳥足になっているのだと思うとなんだか面白い、と思った。
「おねーさん、おねーさん、一人?」
突然、スーツ姿の酔っぱらいに歩くのを遮られる。
「おねーさん美人だねぇー! 一緒に飲もうよぉ」
なんとも典型的なナンパだが、酩酊状態であればこういった行動も致し方ないのだろう。
「邪魔です」
一言の元に酔っ払いを避けて進もうとするが、一緒にいた飲み仲間らしき二、三人のこれまた酔っ払いが道を遮る。
「そんな冷たいこと言わないでぇ。こいつ最近振られたばっかりなんですよぉ」
それは可哀想だけれど、私は家に帰りたい……と思ったとき、ふいにそれは割り込んできた。
くすんだ緑色のジャケット
「あんたら、悪いがこいつは諦めてくれ」
その一言で、目をパチクリさせて彼らは逃げるように消えていった。
「さすが、凄んだ迫力が違いますね。本職の人は」
少し楽しそうに、おかしそうに言われる。
「別に。それよりこれ、渡すの忘れてたんで」
そう言って男がポケットからガサガサと出したのはクシャクシャになった万札たち。何枚あるのかはよく分からなかった。
女が心当たりが無いというように首をかしげると、男はもどかしそうに付け足した。
「治療代……。払ってなかったんで、一応、足りるか分かんないすけど」
「あぁ、そんな、私が勝手にしたことですからいりませんよ」
断ると、男は無理やり女のカバンにそれを押し込んでくる。
「ちょ、ちょっと、わかりました、受け取ります、受け取りますから」
ぐいぐいとねじ込まれて少し動揺しながら女は金を受け取り、出来るだけシワを伸ばしてから丁寧に財布の中にしまった。
「てっきり、帰りが遅くなったから心配で後をつけてくれているのかと思っていたのですが、これを渡すために追いかけて来てくれたんですね」
財布をカバンにしまいながら心なしか残念そうに言うと、男は口をへの字にして居心地が悪そうにそわそわする。
「……別に、あんたがいつ死んでもいいのは知ってますけど、俺としては、今の仕事がなくなると迷惑っつーか。あんた、危機感ないし」
「あぁ、じゃあやっぱり心配してくれたんですね。ありがとうございます」
珍しく、笑って、女が言うので、俺は思わず目を細めた。
結局そのまま女の家まで送ることになって。せっかくなら後をつけるのではなくて隣にいたら良いという提案にも従うことになった。
二人で並んで歩きながら、ぽつぽつと他愛のない会話をする。一つの話題が終わると、また少ししてから女が新しい話題を出す。そうやって途切れ途切れの会話が続いていく。
「──あんた、食べるの早いですよね」
「そんなことないですよ。どちらかと言えば遅いほうだと思います。学生時代も大抵食べ終わるのは最後でしたし……」
「でもさっき店に入った時、すぐ出てきたじゃないですか」
「あぁ、それは、外で食べるのあまり好きじゃないんです。人が多くて落ち着かないというか。周りの音とか光が多くて気になってしまって。美味しそうなお店だから入ってみたんですけれどね。あまり味わえませんでした」
「繊細なんすね」
「そういうわけでは……。まぁ、確かに人より過敏かもしれませんが……。その分、鈍感なところもありますから」
「あー、なるほど?」
確かに感情面で言えばかなり鈍感なようにも見える。表情に出すのが苦手なのか、本当に感じていないのかは、俺には分からない。
「あ、家、見えてきましたね」
角を曲がるとちらほらと明かりの付いているマンションがある。
「じゃあ、俺はこれで」
そう言って立ち止まると、女は数歩行き過ぎてから振り返った。
「部屋まで送ってくれないんですか?」
街灯の逆光で、表情は見えない。
俺は声を上ずらせながら返事をした。
「あっ、え、送り、ます」
その返事に満足したらしく、そのまま少し前を歩く。
分からない。この人がなにを考えているのかやっぱり分からない。反対に俺のことは随分と見透かされている気がする。勘違いだろうか。
数百メートル、時間で言うなら二、三分の短い距離を歩いて、マンションの目の前について。それでも女は振り返らない。
マンションはオートロック式だ。自動ドアを開けて、階段を登って。
「じゃあ、これで」
部屋の扉の前で、俺はもう一度言った。
けれど彼女はちら、とこちらを見上げると、鍵を開けて言った。
「どうぞ」
【13】
「おはようございます」
気だるげに目をこする女が隣で目を覚ます。
いったい何でこんなことになっているんだっけ。いや、別に何一つ昨夜の出来事を忘れたわけではないのだ。
あの後、女に誘われるまま部屋の中に入って出された茶を飲み、そして、あの吸い込まれるような黒い目にジッと見つめられて。それで、俺からこの人に手を出した。
触れるようなキスをひとつ。
俺の指先は震えてた。でもあの人は静かに目を閉じただけ。
「強姦する趣味は無いんだが……」
何も言わない彼女の意図が分からなくて俺はそんなことを言った。俺だけの意思でも、この人を抱くことは出来て、そしてこの人は特に抵抗する気もないのだ。でも、俺はそんなことがしたいわけではなかった。でも、そんなこと、で無いのなら、望んでいた。
彼女は答える。
「私も、意味もなく男を部屋に入れる趣味は無いんですよ」
薄く笑っていた。少し楽しそうだった。からかっているのかもしれなかった。
「……先生に、そういう形で思ってもらえるような男じゃない」
一度は殺そうとした。助けてもらったのに。二回も、助けられた。それでも見捨てようとした。
俺がこの人に惹かれる理由は簡単だったが、この人が俺を好きになる理由はどこにも無いはずだった。頭の良い先生はそんな俺の意図をすぐに汲み取ったらしく、否定はしなかった。
「出会いは最悪かもしれませんね」
遠くを見ながら彼女は言う。
「でも、あなたを恨むことが出来なかった。私を殺そうとして、きっと本当に殺すつもりだったのでしょうけれど、それをためらったあなたの目が忘れられないのです。あなたを、優しい人だと言うつもりはありません。善人だとも。けれど、人を殺して生きているあなたという人を、気づいたら私は、ずいぶんと心の拠り所にしていたのです」
静かに、淡々と告げられた心の内に動揺しながら、うまく言葉を返すことも出来なかったが、嬉しかった。
そうして、俺はやっと許された気がして安心しながら彼女を抱きしめた。初めてちゃんと名前を呼んで、昼間は見られない彼女の表情に心臓がうるさくなった。
俺みたいな人間が、こんなに幸せで良いのだろうかと思いながら、それでも、俺を思ってくれる彼女を不幸にするわけにはいかない。
ただでさえ、こんな世界に巻き込んでしまったのだから。
俺は彼女を必ず守ろうと誓った。
かわりに自分が死ぬことになってもかまわないと、心から思って。
【14】
「かすみ~。今日はちょっと遅くなるかも。久々に上司に飲みに誘われてさ」
彼女の名前を呼ぶ間柄になってから、半年が過ぎて俺たちは一緒に暮らしていた。病院は順調に続いていて、最近は口コミで患者が増えてきたので少し忙しくなってきたが、二人でなんとか回せている。
俺はもっと彼女を手伝える仕事を増やそうと、時間のある時は看護の勉強をしている。いずれは大学に行って看護師資格を取ることも考え始めた。幸いこの仕事だと金はある。勉強は簡単ではないが、家でも職場でも分からなければ教えてくれる優秀な先生がいるので案外苦しくない。
「帰れそうな時間分かったら連絡するから」
「うん。ゆっくりしてきて。面と向かってお話するのは珍しいんでしょう?」
緑茶を温めるためのお湯を沸かしながら彼女は穏やかに微笑む。目のクマはだいぶ薄くなった。
「じゃあ、いってくる」
玄関で靴を履いていると、彼女は火を止めてパタパタと上着をもってやってくる。
「忘れてる。もう11月なんだから、ちゃんと着ないと体が冷えるでしょう」
「あぁ、そうだな。……そういえば、そろそろそのジャケットも買い換えようかな」
あちこちが擦り切れて白くなって、もう長いこと着ているので保温性も下がっている気がする。
「良いかも知れないね。今度、一緒に買い物いこうか。私も冬物のブーツを新しく買いたいと思っていたの」
「お、いいね。じゃあ今度の休みに行こ」
ついでに個室のちょっといい店でも予約して、早めの夕食を食べて帰ってくるのもいいな。そしたら、その後は家でゆっくり……。なんて頭の中で算段をつけつつ、俺はジャケットを着た。
「次のジャケットもその緑色にするの?」
「いや? 特に決めてないけど、目立たない色のほうがいいかな。じゃ、行ってくるよ」
「うん。いってらっしゃい」
上司から指定された店に行くと、店員に案内され個室に入る。扉をあけると既にほろ酔いになっているスーツ姿の男があぐらをかいてくつろいでいた。
「加瀬ぇ。よく来たなぁ」
声のトーンと表情から上機嫌らしいことはすぐに分かった。
「なにか良いことでもあったんですか?」
隣に座り、ひとまずビールを注文してから尋ねてみると、サングラスは嬉しそうに喋りだした。
「いやぁ。思ったより長く元気にやってるみたいだから安心してよ」
部下の心配とはまた珍しい。
「聞いたぞぉ。柳先生から、最近は色々と出来ることが増えてきたんだって? ただの用心棒じゃないってすごく褒めてたぞ」
「まぁ、そうっすね。出来ること多いほうが、先生の負担減らせるんで」
二人で過ごす時間も増やせるし。
「……正直、こんなに長く持つとは思ってなかったんだよなぁ」
言いながら更に酒を煽った。あまり強くもない酒を、今日は珍しくよく飲む。まぁ事務所もそう遠くないから送って行くくらいのことはするつもりでいるが、それよりも口ぶりに違和感があった。
「ひどいなー、そんなに病院が似合わないっすか。俺」
深刻な調子にならないように探りを入れてみると、酔っぱらいは見事にボロをだした。
「病院じゃなくて、柳先生がさ。ちょーっと最初にお話したときに、危ない感じっていうかぁ、こりゃ加瀬もバイバイかな~と思ったんだよねぇ」
「は、え? バイバイって、それ、つまり」
思わず言葉を詰まらせてしまう。けれども言葉の真意を想像すれば酔いも一気に冷めることを言われているのだから当然だ。
「いやぁ悪かったって。でもお医者先生が入ってくれるのと、お前だとなぁ。お前、腕は良いのにコロシは時々やらかすだろぉ。だからいつまでも下っ端なんだよ! このぉ!」
この際、酔っぱらいの嫌味はどうでもいい。殺しでたまにやらかしてるのも事実だ。それより、なんだ? 先生が組織に入るかわりに俺が死ぬ予定だったってことか?
因果関係が分からない。確かに個人の価値としては先生のほうがはるかに上だろう。正規の免許を持ってる医者で後ろ暗いところが無いのに、この業界に引っ張ってこられることなんてそうない。始末するより、本人の意志ってことにしてこっちに巻き込んで、俺を見張りに付ければ下手なことはしないだろうと踏んで派遣したんじゃないのか。
「……酒、もっと飲みますよね。俺てきとうに良さそうなの頼みますよ」
酔え。もっと酔って明日には何も覚えてないくらい酔え!
「あぁ、ありがとぉなぁ」
「いえいえ、いつも世話になってますから、ね」
【15】
半年前──所属のヒットマンを救助した女、名前は『柳かすみ』
聞き覚えがあったので過去の資料を調べる
すぐに女の正体が判明
柳かすみは5年前、同ヒットマン加瀬 優が殺した男の元恋人。柳が作為的に加瀬を救助した可能性を考え、要観察。
本日2回目の接触 柳が所属ヒットマンを殺害する蓋然性ありとして対処。
「お嬢さん、手荒くしてすみませんね。ですがうちとしても、スタッフが減ると何かと困るもので」
煌々と照らされた倉庫の中で、ブルーシートの上にある椅子に座らされて、腕を後ろ手に縛られた上に、こめかみには拳銃が当てられている。
「しかし、加瀬の報告通り驚くほど抵抗なさらない。急に車に連れ込まれて悲鳴一つあげない方は初めて見ましたよ」
柳かすみは、拳銃に怯える様子もなく、ただ話している人間を、乱れた髪の隙間からじっと見ているだけだった。それだけで、表の人間とは思えない様相だった。
「……一回目の接触でしたら、加瀬の提案通りあなたのことは放置しておくつもりだったのですが、二回目の接触、あれ、わざとでしょう?」
返事はない。けれど。
「調べさせて頂きました。あなた、五年前に加瀬と既に会っている」
ぴくり、と肩が動く。
「殺された彼とは、恋仲だったそうですね。そしてちょうど、殺されたあの日に喧嘩をしている。ここまでは事前調査で分かっています。ただ、あの晩に何があったのか、加瀬の報告では目撃者はいなかったと聞いています。ですが、その後の報告で第一発見者が柳かすみさん、あなたであることは分かっています。事情聴取では待ち合わせに遅れて彼が亡くなった後に発見したと仰ったそうですが、私の推測では、あなたは彼が亡くなる瞬間に居合わせたのだと考えていますが、どうですかね?」
柳かすみはそれを聞くと、薄く笑った。口元だけが。そして嘲笑するように言った。
「あなた達って警察とも仲がいいんですね」
「……えぇ。色々な方と仲良くしておりますよ」
はぐらかした……? いや、今それをする意味がないはずだ。そう思っていると、柳かすみは続けてこんなことを言い出した。
「病院とは、あまり仲が良くないみたいですけれど。どうでしょうか?」
「は……それは……」
ぎらぎらと目を鈍く光らせて、口調だけは至極丁寧にそれはこちらを値踏みしている。
「私、少し早いけれど開業したいと思っているんです。人の多いところで気を使いながら働くより、自分が上に立つ方が楽で良いでしょう。小さな施設で良いんです。そこで馴染みのお客さんを作っていけたらな、なんて思ったり」
穏やかに、自らの価値を天秤へとのせてみせる。
「仲良く、致しませんか?」
下手くそな虚偽報告をするヒットマン一人と、社会的信用を持って虚偽書類を用意してくれる医者ならば、その価値は天秤にかけるまでもない。
縄を解き、家まで送り届けると提案するがそれを丁重に断られる。
「おそらく、迎えに来てくれますから。あなたもお気づきでしょうけれど」
車に乗せたところを見られたのに気づいていた。あの状況で、それを認識するほどの余裕があったとは。
「先生は、カタギとは思えませんな」
敬意を込めて言ったつもりだが、どう受け取られたかは分からない。
「私は五年前のあの日、死ぬはずだったのです。だからこの先いつ死んでも、案外長く生きたと思えるでしょう」
真っ白い顔色と合わさって、まるでゾンビか幽霊のような言いようだと思った。すでに自分は死人であり、もはや恐れるものは無いと。加瀬は、恐ろしい女を敵に回してしまった。
「必要であれば、先生のお使いになれそうな道具を用意しますが、銃器は扱いづらいでしょうから他の……すぐに用意できるものもありますので」
「お気遣いありがとうございます。けれど、大丈夫です。それより、一つお願いが」
「はい。なんでしょう」
「私の病院に、警備をしてくれる人を派遣してもらえませんか。治療に文句を言われて暴れられても面倒なので。そういうことに慣れている方で……そう、私の顔見知りだと安心なのですけれど」
じっくりと、自分のテリトリーに入れて復讐を遂げるつもりか。
出来ることなら、先生には加瀬を殺しそこねてもらって殺人未遂を盾に業界に引きずり込み、加瀬にはしばらく遠いところで働いてもらうとありがたいんだが、そうはさせてくれないか。
今すぐ殺しに行ってくれれば、先生が加瀬を殺れるとは思えないし、その力量差なら先生も殺さずに無力化出来るんだが。どうにも、守るものがない人間というのは扱いづらい。
「──病院の方、手はずが整ったら改めて連絡します」
「えぇ、よろしくお願い致します」
【16】
ガチャガチャ、と鍵の開く音がする、まだ帰る連絡はきていない……と思うが、酔って忘れたのだろうとそれほど気にせず豆腐を切って味噌汁にいれ、手を洗う。
玄関のドアが開いて、閉まる音がして。
けれどただいま、という声はなく、少しおかしいと思って様子を見に行こうと顔を上げたら、蒼白な顔をした恋人が立っていた。
「優! びっくりした。ひどい顔色……悪酔いしたの? とりあえず座って、今あたたかいお茶をもってくるから」
ちょうど温めたばかりの緑茶がある、と思って台所へ向き直るが、気配もなく近づいてきた恋人に腕を掴まれて振り返る。
「どうしたの? 寂しくなってしまったの?」
優しく笑いかける彼女に、加瀬はなにを言えばいいか分からなかった。けれども、知ってしまった彼女の過去を、己の犯した罪を、知らないふりは出来ないと思った。
なにか、言葉を、伝えたいと思って、結局ずいぶんと詰まらせながら口走った。
「かすみ……俺のこと、……俺の、こと、さ、……す、好き?」
彼女は少し驚いて目を瞬かせると、すぐに答えた。
「好きだよ」
嘘をついているとは、思えなかった。
一度だって、彼女が嘘をついたと思ったことはなかった。
でも、最初から全てが嘘だったのなら、これ以上、彼女にそれをさせたくはなかった。
「……俺も、好きなんだ。ほんとに」
愛している。だから。
「俺のこと、殺していいよ」
俺に出来るのはそれくらいだった。
頭の良い恋人は、その一言で全て気づいて顔色を変える。あとずさり、台所に手をついて、ずるずるとその場に座り込んだ。小さな肩が、震えていた。
彼女の目線に合うようにしゃがんで、俺は必死で言葉を吐き出した。
「ずっと、つらい思いさせてたんだな。嫌だったろう。仇の手当をして、優しくして、一緒に働いて、それだけでも苦痛だろうに、家でも一緒で、求められれば抱かれてやって。でも、もうそんなことしなくていい。もう俺は充分お前のことが好きだから、いつでも殺せるよ」
ジャケットに入れていた拳銃を出して、恋人に差し出す。
「使い方は分かるって前に言ってたよな」
震える手で、彼女はそれを受け取る。
そうして、自らの手に握られた銃をじっと見て、小さくこぼした。
「信じてもらう資格は、ないでしょうね」
彼女は顔を上げて、俺を見る。なぜ泣いているのか俺には分からなかった。
「かすみ……?」
「なんであなたを私の病院で働かせるように言ったと思う?」
「それは、そのほうが殺しやすい」
「じゃあなんで半年も、何もしないで恋人になんかなったと思っているの」
「それも、そのほうが殺しやすいだろう。俺は殺し屋で、これでもプロだ。油断させなければ、殺しそこねる危険があった。そこら辺を甘く見積もるようなことはしないだろ」
そうだ。彼女のそういうところはよく知っている。
彼女のため息の種類で、だいたい何に疲れているのか分かったり、眠い時特有の声であったり、得意な仕事、少し苦手な仕事。ずいぶんと彼女のことが分かるようになったと思っていた。
けれど一番大事なことは分かっていなかった。
「全て、違うと言ったら……あなたは信じられないでしょうね」
妙なことを言いながら、微笑んで泣いていた。悲しんでいるように見えた。どうしてだろう。
「違う? 今までの生活のことだよな。分かってるよ。恋人の仇を討つために嘘の生活をしてきたんだろ?」
自分の吐く言葉に責める響きが一つもないことに、彼女が泣いているのだと俺は気づかなかった。だから重ねて言った。
「もうそんな暮らしはしなくていい。もしかしたらかすみの……先生の考えていた計画とは少し違ってしまったのかもしれないが、俺は、逃げないから」
一言一言を噛みしめるように、伝えた。
「私が望んでこの暮らしをしていたと言ったら?」
「え……」
俺は耳を疑う。望んで? 偽りの生活を?
「私が、一つも嘘をついていないと言ったら、あなたは信じられる?」
「なにを……」
馬鹿なことを。そんな俺にだけ都合のいい話はないだろう。
「信じられないでしょうね。ずっと一番大事なことを隠していたんだから。私はずっと、あなたを殺す理由を探していたの」
殺す理由? そんなのもうはっきりしてる。お前の大事な人を俺が殺した。
「だけど、知れば知るほどあなたを好きになる。人殺しだと知っているのに! あの人を殺したのに! 分かっていても、あなたの優しいところを知ってしまったら……もう、憎むことなんか出来なかった!」
悲痛な顔をして、自分で自分を責めて、彼女は泣き叫んでいた。
「最初に、あの人を殺した後に、私も殺そうとして、それをやめたときのあなたの目が、忘れられない。冷たい目で私を殺そうとしておきながら、ためらって、見ず知らずの女が自分のことを黙っていると信じて、許してしまったときの、あなたのことを、忘れられない。悪魔みたいな女なの。あの瞬間、目の前で死んでいる彼よりも、あなたの心に惹かれてしまったんだから」
「どうして、どうしてあの時、私も殺してくれなかったの」
彼女の呻くようなその言葉に、俺は何も返せなかった。ただ、泣いて身を縮めるその小さな体を抱きしめる。
腕の中で彼女は、まだ俺の身を案じているらしく、言い募った。
「もう何も信じられないかもしれないけれど、あなたを殺すつもりが無いことはもう伝えているから。あの気が抜けると口の軽くなる、上司の人に。けれど、それも信じられないかもしれないから」
そんなことは、俺にとってはもうどうでも良かったけど。
「どうぞ、私を殺して」
それは彼女にとって最大の、身の潔白を証明するための道だった。
恋人の命を奪う脅威にならないために唯一出来ることだと思ったから。
「じゃあ、いつか殺したくなったときのために、側にいてくれ」
そう言うとまた、ひどく泣き出してしまった彼女の涙が、今度はきっと悲しいものではないと信じて俺はもう一度強く抱きしめた──。
【『どうぞ、私を殺して』終】

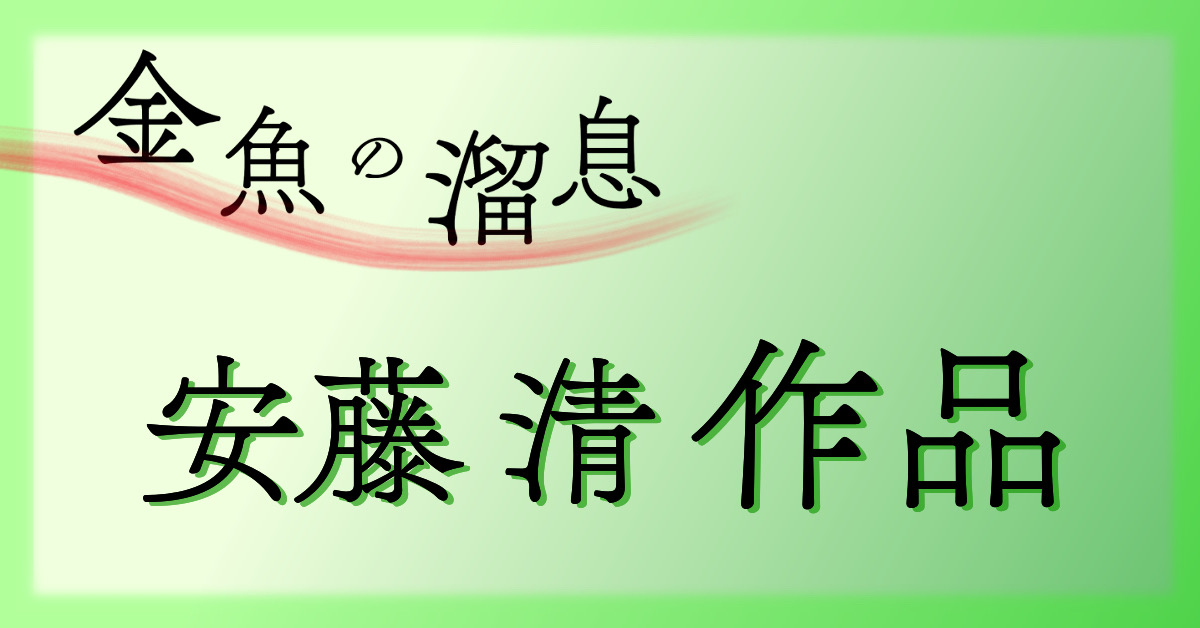


コメント