掲載日 2024/12/08
読了目安 20分
注意事項 性的な描写があります
【あらすじ】
美しく気品のある少女、カオル。しかしその佇まいとは裏腹に人をからかうような話し方をしたかと思えば、野生の獣のような警戒心を垣間見せる。その理由を、少年 竜《リュウ》は三度目の偶然によって知ることになる。
「逃げているの」と言って笑った美しい少女が不器用な少年に救われる話。
『三度の逢瀬、事切れるまで』
【一話:逢瀬】
「相変わらず痛そうだね」
後ろから降ってきた声に顔をあげると美しい相貌に胡散臭い笑顔をたたえた女がいた。
「お前かよ」
なかばため息を付きながら視線を戻す。
「隣に座っても?」
どうせ断っても意味がないことは、このあいだ一度話しただけで分かっていた。
そう。俺はこの女と話すのはこれで二回目だった。にも関わらず、初めて会ったときから図々しい女は二度目ともなるとまるで気心の知れた友人かのように話しかけてくる。
「ねぇ、隣、いい?」
俺の不満など素知らぬ顔で、女は再度尋ねてくる。
「……神社の階段は座っちゃいけねぇんじゃねぇの」
せめてもの抵抗は、一度目に女が言った嫌味をそっくりそのまま返してやることだった。
けれども女は平然と言った。
「へぇ、知らなかった。どうして座っちゃいけないのさ」
「おまえ……」
俺は思わずポカンと口を開けてしまった。
「隣、いい?」
「……、……好きにしろよ」
みじんも断らせる気のない女は丁寧な所作で石階段の上にハンカチを敷くと笑顔のまま座った。
明らかに高そうな、きっといい香りのするであろうハンカチ。その上に座る、質のいい生地で作られたシワ一つ無いワンピースに身を包んだ女。
血と土で汚れボタンの取れそうな学ランを着た俺とは随分ちがう生き物。
けれども、少なくとも一度目に会った時、この女は俺と同じ目をしていた。今の悠々とした笑顔はなく、外敵を警戒する獣のような無表情。
しかし、人気のない神社の石階段に座る俺を見つけると、一瞬の激しい敵意を向けた後、それを隠すように笑顔を作り、歩調を緩めた。
声を発するまでに少しの間があったのはおそらく息を整える必要があったから。
女は努めて穏やかに、親しげな声色で言った。
「その制服、西高の人でしょう?」
見ず知らずの他校の男が明らかに喧嘩をした後だと分かる痣を作っているというのに女はまるで恐れる様子がない。
俺は答えなかった。けれど奴はそれに気を悪くすることもなく更に話しかけてきた。
「手の甲まで赤くなってる。何をしたらそこまで血がつくの?」
思わず俺は自分の手の甲を見た。そこにはちょうど拳を握りしめて殴った時に擦りむけたところが真っ赤になっていたが、確かに手の甲まで赤くなっていた。こんなところで人を殴った覚えはない。
はて、と首をかしげていると女はいつの間にかすぐそばに立っていて、俺の顔を覗き込んだ。
「あぁ。口もとの血を拭った時についたんだね」
距離の近さにぎょっとしながら俺は座ったまま少しのけぞった。
「どうして喧嘩したの?」
なんだってそこまでしつこく話しかけてくるのか分からなかった。が、ともかくとして俺は面倒だった。
やはり答えないままいると、奴は静かになった。やっと黙ったかと思って、それでもその場からいなくなろうとはしないので何をしているのかと気になって俺はあろうことか視線を向けてしまった。
ちら、と一瞬 目が合った。
しまったと思ったのも束の間、急いで目をそらしたが、もはや女の視線から逃れることは出来ない。見なくても女が黙って俺を見ていることは分かっている。
微動だにしない。
俺はさっさと立ち去ってしまえばいいものを、すっかりあの視線に射竦められて身動きが取れなくなっていた。
「……」
結果、沈黙に耐えられず、間の空いた返事をする羽目になった。
「……、前に、殴ったやつに絡まれたんだよ」
女は間髪入れずに再び尋ねてくる。
「その前のときはどうして喧嘩をしたの?」
「っ、お前には関係ないだろうが!」
やっとのことでそのセリフを言うと、女は俺の怒鳴り声をまるで意に介さず、笑ったまま、そうね。と短く返した。
「あなた、名前は?」
突然、切り替わった質問に面食らって、また間を置いてから俺はやっとのことで返した。
「聞いてばっかりじゃなくて、お前から名乗ったらどうなんだ」
「私はカオル。いい香り、の難しい方の薫ね」
思ったよりあっさり答えられて、俺は諦めて名乗った。
「俺は、ヤクシ──薬師 竜だ」
「リュウって言うの。なんだか似合ってる名前ね」
満足気に女は言った。
「で、薫サンはなんだって俺に絡んでくるんだよ」
うっとおしさと、わずかの興味に負けて。わざとらしく頭を掻きながら尋ねる。女はやはりあっさと答えた。
「暇なんだもの」
「は?」
「あなたもこんな所に一人でいるんだから、どうせ暇なんでしょう」
「俺は別に──……」
暇じゃない、とは。
ただ、傷だらけの顔を見てまた悲しそうな顔をする母親がいる家に帰る時間を少しばかり遅くしようと思って。確かに『暇』を潰しているのに違いなかった。
「だからお喋りに付き合ってくれたっていいでしょう。どうしても、その血が出てる唇が痛くて話したくないのなら無理にとは言わないけれど」
「こんなのは別に……」
痛いということにしておけばこの得体のしれない女と無駄話をしなくて済む、ということよりも、先に疑問が湧いた。
「お前は、なんでここにいるんだ」
見たところ年は同じくらいだろう。服装からして不良少女ということもない。むしろどこかのお嬢様と言ったほうがしっくりくる。それがこんな人気のないところで、こんな夕暮れ時に『暇』を潰さなければいけない理由とはなんだろうか。
女は風に煽られるスカートを弄びながら言った。
「逃げているの」
なにから? と聞いたら、きっと女はあっさり答えたに違いない。
けれども俺は聞かなかった。気になりはしたのに、聞いていいとは思えなかった。
女は、薫は、あまりにも、遠いところを見ていたから。
そうして二度目に会った時も、あいつは『なにか』から逃げていたが俺はそれを聞くことは出来なかった。他愛のない問答を繰り返し、お互いに『暇』を共有する。それだけの間柄。たった二回だけの浅い関係。
それは、三度目の偶然によって形を変えた。
「南条! お前、また俺の母ちゃんにいらねぇこと言っただろ!」
その日は、数少ない友人による母親への密告を批難しながら帰り道を歩いていた。
「竜が喧嘩の原因を話さないからだろ。毎回お前の母さんに申し訳無さそうに何があったのか聞かれる俺の身にもなれ」
「ほっときゃいいだろが!」
「そうはいくか。大体、この間のだって絡まれてる女子助けただけだろ。最初っからそう言えば良いんだよ。ちっと殴りすぎではあるが、あんなに親御さんを心配させずにすむだろうが」
母親のことを出されると、どうにも強く出れなくなってしまう。だからといって、自分から原因を話すのはなんとも格好悪い気がして。「だから許してくれ」と言っているようで、結局むだに心配をかけている。
「原因と、殴ったことは、関係ないだろ」
小さい声で、そんなことを言った時それはいきなり現れた。軽い衝撃と聞こえない程度の驚いた声。
「おまえ……!」
ぶつかってきたのは、見知った女。けれどもいつものような余裕たっぷりな表情も、軽やかな淡い色合いのワンピースでもなかった。
重苦しい紺色のセーラー服に、真っ白のスカーフ。その色の組み合わせはこの辺ではたった一校しかなく、それも私立で中高一貫の女子校として金持ちが多いことで有名なところだった。
けれども、そんな事実よりも、すぐに浮かんだ憶測によって、後ろにいる友人から女を隠す羽目になった。
「しりあい、か?」
「あぁ、わりぃ、俺ちょっと用事あるからお前は先帰れ」
「……おーけー」
こういうところで詮索しないのが、友人である所以だ。察しの良さに感謝しながら腕の中に隠した女に声をかける。
「おい、おまえスカーフどうした」
結ばれているはずのそれは、随分と不格好に乱れていた。服装と、青ざめて息を切らしていることに関係があるのなら見過ごすわけにはいかない。
いつもの饒舌さはなく、二回ほど、はくはくと空を食む。
「逃げているのか」
憶測が現実に寄りはじめ、怒りを抑えるのが限界に近づいていたが、ぎりぎりでなるべく声を荒らげないよう気をつけながら尋ねると、薫は俺の腕を握りしめながらゆっくりと息を吐いて、呼吸を整えると顔をあげた。
まだ青ざめていたが、目線はしっかりと俺を見留ていたし、いつもの笑顔はなかったが、怯えてもいなかった。
初めて見た時の無表情なあの横顔が思い出される。
「そう。逃げて、いるの」
硬い声でそう言った。だから俺は、やっと聞くことができた。
「なにから」
薫は答えようとして笑った
貼り付けた笑顔ではなかった
心から笑っていた
あらゆる憎悪を込めて
激しい恐怖心とわずかの虚栄によって
それ以外の正しい表情が分からなかった
「──お父さんから」
【二話:事切れ】
薄汚れた石造りの鳥居に寄りかかって、石段を駆け上がってくる男を待っていた。
「そんなに急がなくても良かったのに」
ぜぇぜぇと息を切って膝に手をつく彼に言うと、ガサガサとうるさいビニール袋を左手に持ち替えて私の手を引いた。
彼は、会ったときからお喋りは嫌いだったし、表情もほとんど変わらなかった。少し眉間にしわがよるだけ。
今まで会った多くの男という生き物とは、ずいぶん違った。
だいたいの男は私を見るとまず一度目を見開いて、そのあと浅く息を吸ってから口角をあげて三度ほど音程の上がった声で話しかけてくる。
彼は、私を見て一瞬の観察をしたあと即座に無関心を呈した。彼にとって私は女ではなく、他人だった。
だから私はすがった。
度重なる父親からの視線。そして上ずった声色でかけられる愛情を示す言葉。
肩に触れる温かく乾いた手の、優しく包むような感覚。
全ては、そこに熱がこもっていなければただの娘に甘い父親。けれども、あの人のそれは弱く美しいものへの加害に過ぎない。
「あの人を恐れている自分がなにより嫌いなの」
彼は神社の隣にある納屋に私を引き込むと、自分の学ランを、神経質に埃まみれの床の上に敷いた。
私はそれをぼぅと眺めながら取り留めもなく喋り続けた。
「知らないことより怖いことってきっと無いと思う。そうじゃない?」
「父親にされたキスの味なんて、覚えていたら、私はずっと男の人が怖いまま」
喋るほどに、彼の背中から怒りが感じ取れた。それでもしばらく黙って学ランのシワを伸ばしていたけれど、ふいに立ち上がって振り返った。
「されたのか」
短い問い。
私は答えなかった。かわりに少し微笑んだ。
それが返事。
彼は狭い納屋の中、たった一歩で私の目の前に来て、肩に触れると止まって見下ろす。
「するの?」
私が尋ねると、彼はしばらく黙って、けれど耐えられなくなったように言った。
「俺も男だ」
ずっとその一言を言おうとしていたんだろうと思うといじらしい。私は思わず少し笑い声を漏らした。けれど彼は微動だにしない。
観念して答える。
「……知ってる。でも、私を自分のものにしようとは思ってない」
彼は、よく分からないという顔をした。
そうだろう。彼にとっては、それは当たり前のことなのだから。
「私は、あんたのことは怖くない。だからお願い。私を抱いて」
彼はそれ以上、なにも聞かなかった。なにも言わなかった。無表情で温度のない瞳で私を見、抱きすくめて唇を重ねた。
セーラーを脱ぐ間、彼も白いカッターシャツを脱いでまだ痣の残る体があらわになる。
私は几帳面に敷かれた学ランの上に手をついて座り、彼を見上げた。
彼は私の前に膝をついて、右手を腰の横に、決して肌に触れないようにおくと、左手で私の肩に触れた。
喧嘩をして、荒れている手
握ったり擦れたりして硬くなった皮膚が私の丸く薄い肩をつかむ。
そして、目線を交わし、もう一度唇を重ねる。
先程まで走っていたのに、彼の唇は冷たかった。春先とはいえまだ寒い、外気で冷えたのだろう。──これが、もしも当然のようにあたたかければ私は恐怖心を抑えるのに時間を要したかもしれなかった。
けれども、幸いなことに目の前の男は、私の知っている優しくて醜悪なそれとは随分と違っていた。
何度かついばむようにキスをして、段々と熱がうつり、私の唇に彼の舌がゆるりと這うのを合図に小さく口をあける。食べられる、とはまさにこういう心地なのだろうと思いながら、口の中を這い回る舌の感覚に慣れず、自然と体に力が入った。
すると彼は即座に身を引いて、無表情のまま言った。
「わるい……」
何を謝ったのか、分からなかった。けれども私は平気だよ、と答えた。
彼はそれに瞬きを一つ返すと視線をはずし、肩を捕まえていた手を離して腰へと絡め、あらわになっている乳房へキスをした。唇で撫でるように、肌とこすれるのを心地よく思っているのか、その輪郭を這う。
「つむじが見える」
ポツリと私が言うと、彼は下を向いたまま少し笑った気がする。
乾いた唇と荒れた手は、私のあばら骨をなぞり胎の真上にある薄い腹をくすぐる。
今度は唇だけではなくて、頬で、鼻で、何もないなかみの音を聞くように押し付けられるそれに、どこか愛しさのようなものを感じた。
「体、たおせよ」
胸にあたるパサパサした黒い髪の毛と、その中にあるつむじをじっと見ていた私のことをふいに見上げて、そう言われる。
私は、少し首を後ろに傾けてあまり彼の学ランをぐしゃぐしゃにしてしまわないように気を使いながら肘をおろし、次いで頭をつけた。
「背中、痛くないか?」
「少し硬いけど、平気」
横たわる私の唇にもう一度軽くキスをすると、彼は少し待っていろと言って白い半透明のビニール袋からガサガサと中身を取り出す。
ローション
コンドーム
ペットボトルの水
「黒いビニールに入れてくれないんだ」
何気なく言うと、彼は首をかしげた。
「くろ? 分かんねぇけど、他のもんと一緒に買ったからじゃねぇの」
「そうかもね」
ゴムだけで事は足りるだろうに。制服を着たまま明らかにその目的でドラッグストアをうろつくのはあまり居心地のいい時間じゃなさそうだけれど、そういうことは気にならない質なのだろうか。
「……ありがとね」
パキ、と少しにぶい音とともにローションの蓋を回して開けた彼に言うと、一瞬だけ目が合って、なんとも居心地の悪そうな顔で「別に」と返される。
ローションを手のひらに出そうと、逆さまにして押すと思ったよりも勢いよくぶにゅりと透明のゆるい液体が出てきて彼は少しびっくりした。驚いた猫みたいになったのでかわいかった。
すぐに何事もなかったかのように手の中でそれを、にちにちと温めてから私に向き直った。再び腰の横に手をついて。触るぞ、と一言いってから膣に触れた。
温かく荒れた手が割れ目をなぞり、私は自分の呼吸が早くなるのを感じて少しの羞恥とともに腕で顔を隠した。
するとすぐに彼の手がとまる。
「顔、かくすなよ」
なんてことを言うのだろうかと思って非難するような気持ちでわずかに顔をあげると、続けて声が降ってくる。
「マジで嫌がってる時に分かんねぇだろ」
「……そういう時は、ちゃんと言う」
押し殺した私の声に、彼は何か感づいたらしかった。目を合わせないようにして答えたのも、彼に気づかれてしまった一因だろう。
「なんだ、恥ずかしーのか」
返事に詰まる私を見ると、少し機嫌が良さそうに、意地の悪い顔をする。
「悪かったよ。そういうことなら隠しとけよ」
しばらく私の小さな突起を指で上下になでさすり、もはや息苦しくなってきて。
「は、ぁ……」
「指、いれるぞ」
狭い納屋の中で私の吐息と彼の低く淡々とした言葉だけが響く。けれどそれも、すぐに埃っぽい木々に吸い込まれて消えていく。
「ぅ、あ、」
「痛いか」
彼は一度指をぬいて、濡れていない左手でローションのボトルをひっつかんで粘液のしたたる右手にそれをぼたぼたと足す。
またあたためて、ぬる、と指が入ってくる。
まだ指一本、それほど痛みはなかった。けれども味わったことのない奇妙な異物感に体がこわばる。
「息を吐くんだ」
彼はなだめるように、乾いた手で私の髪をなでる。
野生の獣みたいな目つきに、傷だらけの体をしているくせに、どうしてそんなに優しい声をしているの。
機械的なセリフしか言わないくせに、どうしてこんなに、優しさが刺さるの。
「いっそ、もっと強引にしてくれて良いのだけど」
ひどい八つ当たり、でも彼は不快に思う様子もなく答える。
「それじゃ意味がないんだろ」
「いみ?」
「戦うんだろ。逃げるのやめて」
「……そうだね」
そうだ。私は二度と男を恐れないために、もはや未知の生き物ではないそれを倒すために、この優しい獣にすがったのだ。
「それなら、これがお前にとって痛くて、苦しいものになったら意味がない。殴られるのにビビってたら喧嘩は出来ない」
「私に、父親に犯されるくらい上等だと思えっていうの?」
「そうだ。それがお前の戦い方なんだろ。じゃなかったら俺が走った意味がない」
優しくて冷淡な獣。やはり私の予感は間違っていなかった。ひと目見たときから、これは野生の生き物だと分かっていた。
「……ね、つづき、して」
彼は目線をもどして私の体内を指でこじあける。
「増やすぞ」
短く言って隙間を広げる指が二本、それぞれが自律して違う方向に動き、体の穴が広げられて、だんだんと、男を受け入れるために形を変えていく。
「あ、ぅあ、あ……」
すぐに、今度は宣言なく三本目の指が入ってきて、奥へと進む。
ぐちぐちと体の中から音がする。もはやローションを足す必要はなくなって、私はこれ以上、この男に恥を晒すのも耐え難く唇を噛んで声を抑える。
快楽を得ることがこれほど羞恥を覚えるものだとは、知らなかった。
けれどもこの恥によって、私はこの先どれほど痛みと嫌悪に苛まれても、甘い吐息と奥ゆかしい嬌声によってあの醜悪な生き物を支配することが出来るだろう。
「もう入りそうだな」
淡々と告げて側に置いていた四角い小さな銀色の包みに手を伸ばす、息を切らす私とは対照的に──いや、彼もまた少し額に汗が伝っている。興奮しているのか、それとも単に神経を使いすぎて疲れたのか。
ピリ、と封を切られた小さなそれ、から丸く薄い膜が出てくる。
カチャカチャとベルトを外す音
ジィ、とファスナーが下りた
私が寝転んでいるところからは、彼がそれをつけるところは見えなかった。けれど起き上がる気力はとうにない。
「いれるぞ」
だからその言葉で彼が準備を終えたらしいことが分かった。
ひたっと彼の両手が私の太腿をつかみ、肥大したそれが、丸い傘の割れ目と私の体の入り口が触れ合う。と、すぐに指とは明らかに感覚の違うなにかが……あついものが、体の入り口を押し広げる。
「っ、く……ぁ、あ」
体は異物をおそれて、それを追い出そうと絞め上げる。にぶい痛みと恐怖に、敷かれていた彼の厚意をぐしゃぐしゃに握りしめて。
──嫌に埃臭さが鼻につく気がする
灰色の匂いだ
窓から射す光を受けて 私の白い息と
無数の埃がキラキラと輝いている──
「だいじょうぶだ」
声とともに、ふいに先程まで見えていた光から、視界が真っ暗になったことに驚いていると、彼は私の頭を抱えるようにして覆いかぶさっていた。
「どうせこんなとこ、誰も来ない。声もだしていい、泣きたいなら泣いてもいい。大丈夫だから」
「だから、ちゃんと俺を見ろ」
息を、うまく吸えていなかったことにやっと気づいて、肺を埋め尽くす大量の空気に驚いて思わず咳き込んでしまう。
「よーしよし、もどってきたな」
子供みたいに頭を撫でられて、ほっとしている自分がいた。
「もう少しだから、今度はしっかり起きてろ」
言われて、私は目元がじわりと熱くなるのを感じながら小さく返事をした。とはいえ、返事と言うにはあまりに短くて、それはほとんどうめきに近かったのだけれど。
一度引き抜かれたそれが、再び私の入り口にあたり、ぐっ、と押し込まれる。
なるたけ拒んでしまわないように、息をはいて、すって。
彼が私の中に入ろうとするのを必死に受け入れる。
はいて
すって
にちにちと広がって、圧迫されて、小さな隙間が痛みとともに少しずつ押されて、内壁に自分のものではない熱を感じる。
ほんの僅かしか入っていないはずなのに、まるで内臓をえぐられているかのような感覚が襲ってくる。
「ぅ、ぐぅ……ぉえ」
口の中で唾液が出てきて喉につまる。思わずもれた嗚咽に彼は少し焦ったようにこちらを見た。
私はうまく言葉を口にできる余裕はなかったから、変わりに手を所在なさげに少しぶらぶらとして見せて意識があることを伝えた。
「……もう少しだから、がんばれよ」
心配そうに励ましながら、協力者は私の苦しみを享受し、目を細め、眉根を寄せる。
二人の痛みが溶け合って、白い息が重なる。
「は、あ、ぅ……う、っ」
ずくずくとしびれるような感覚と共に、ゆっくりと体の奥が侵害されていく。
痛みの中、息を止めてしまわないよう少しでも口をあけて空気を吸い込もうと思った時。
──今までとは比べ物にならない激痛が走った。
「あぁっ!」
悲鳴に近いそれ──身を縮め、涙は勝手にぼろぼろとこぼれていく。汗が吹き出して、体が、破壊されようとしていることを警告していた。
けれども彼は、尋ねることはしなかった。ただ、苦しむ姿から僅かも目をそらさずにいた。
「い、っ……ぐ、ぅ……」
やめてはくれない
とまってはくれない
体の中を裂かれる痛みにもがく私にキスをする。頬に──涙の上に。
苦痛と慈愛の間で
彼は私を突き刺した
黒い制服の上に、赤い体液が滲む。
ぴったりと私達は重なり合っていて、彼が深く息を吐いたので、それは終わったのだとわかった。
そうして
私は中学最後の春
処女を散らせた
三度だけ逢った男によって
この先も生きているために
この苦界から逃げてしまわぬために
そしてあの醜悪な鬼を支配するために
愛しい獣に我が身を喰わせ
私は天人となる
【エピローグ】
白い背中──慣れたように少し前かがみになってブラジャーをとめる。
ただし俺の制服の上で器用に横座りして。
別に構わないが、そろそろ少し寒い。
「あぁ、ごめんね」
視線に気づいたようで、そう言って下着姿の女は立ち上がって制服の上から自分の靴の上に移動した。
「いいけど、……」
痛むか、と聞こうと思ってやめた。痛くない訳はないから。それをわざわざそいつの口から言わせる必要はなかった。
プライドの高い女だ。
きっと、こいつは自らの父親を地獄に落とすまでどんな苦しみを背負うことになってもそれをやめないんだろう。
今ならこいつが俺に話しかけた理由が分かる。同じたぐいの匂いがしたに違いない。
俺たちはただ生きるというだけのことに、あまりにも血生臭さを伴わなければいけない星の元に生まれたらしいから。
「やっぱり埃すごいね、家の人に怒られない?」
いつの間にか何事もなかったかのようにきっちりと制服を着ていた女は俺のホコリまみれで真っ白になった学ランを見て言った。
「元から汚ねぇし、まぁ、母ちゃんに聞かれたら喧嘩したって言っとけば呆れられるぐらいで済むだろ」
なにせ今日は新しい怪我がない。
「そう。それなら良いけど」
静かに女は返して、俺たちは納屋を出た。外はちょうど西日が眩しい時間で俺は思わず顔をしかめ、すぐに目をそらしたが、隣にいる女はまるで表情を変えていなかった。
女は最初から太陽の方を見ていなかった。
「ありがとね」
俺の目をまっすぐみて、そんなありきたりの言葉を言うと、ふいに一歩近づいてそれは少しだけかかとをあげた。
──それを合図に俺たちはまた他人に戻る。
【『三度の逢瀬事切れるまで』終】

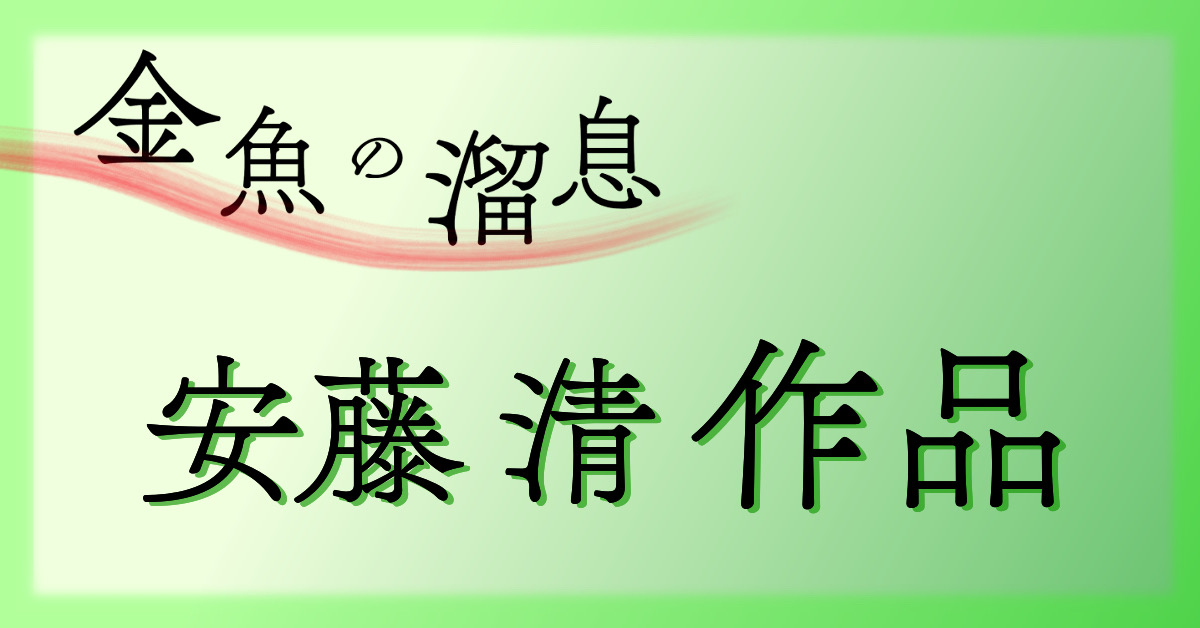

コメント